※書きかけの記事です
この記事は Headphone Zone に掲載されている Understanding the Language of Audiophiles(オーディオマニアの言葉を理解する)を翻訳したもので、少しコメントをつけました。
外国語的な表現も多々あるので意訳しています。
- ベース(Bass; 低音域)
- ハイス(Highs; 高音域)
- ミッドス(Mids; 中域)
- エアリー(Airy; 風通し、空気感)
- ナチュラル(Natural; 自然な)
- アナリティカル(Analytical; 分析的な)
- バランス(Balance)
- ブロウト(Bloat; 膨張/肥大化した)
- ブライト(Bright; 明るい)
- コンゲッション(Congestion; 混雑した)
- クリスプ(Crisp; パリッとした)
- ダーク(Dark)
- ディケイ(Decay; 減衰)
- デプス(Depth; 深さ、奥行き)
- ディテール(Detail; 細部)
- フォワード(Forward;)
- ファン(Fun; 楽しい)
- カラード(Coloured; 色付けされた)
- ハーシュ(Harsh; きつい、トゲトゲした)
- イメージング(Imaging; )
- ラッシュ(Lush; 豪華な)
- マイクロフォニックス(Microphonics; )
- マッディ(Muddy; )
- オープニス(Openess; )
- パンチ(Punch; )
- シビラント(Sibilant; )
- サウンド・シグネチャ(Sound Signature; )
- ティンバー(Timbre; )
- トランスペアレント(Transparent; )
- ウォームス(Warmth)
ベース(Bass; 低音域)
簡単に言えば、約60Hzから250Hzの間の周波数のことです。人間が聴き取ることができるいくつかの周波数帯域(20Hz-20kHz)の中で最も低い部分です。
良い低音というのは、明瞭でパリッと(crisp)していることで、全体的なサウンドを支配してしまわない事が最も重要です。
‘ブーミー’ や ‘マッディー’ はベースを否定的に表現する言葉です。
ハイス(Highs; 高音域)
ハイス(高音)はオーディオ周波数スペクトラムの上部です。
フルートやバイオリンの音が良い例です。
支配的な高音はサウンドを明るく(bright)、またはトゲトゲしく(harsh)する傾向があり、レモンをかじったときのように表情が歪んでしまうでしょう。
良い高音を伴った音楽は豪華さ(lush)と心地よさ(sweet)を提供します。
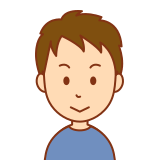
日本語では高音が「キラキラしている」と表現する人が多い印象です。
ミッドス(Mids; 中域)
中域は、楽曲の中心的な部分を聴くことを可能にする周波数です。
ボーカルや、ギター、フルートなどの楽器を含む部分。
望ましくない中域は、色付けされた(coloured)、曇った(clouded)サウンドになってしまいます。ジャンルに関係なく、ミッドは全体的な印象を作ることも、破壊することもできてしまうのです。
エアリー(Airy; 風通し、空気感)
オープン型(開放型)ヘッドフォンにみられる開放性や空間を説明するために通常使用される用語です。
音が一方向的ではなく、広い距離を伝わっているように感じられる場合は、エアリー(風通しの良い、空気感のある)と表現できます。
この用語は、Audeze LCD-3、Beyerdynamic T 5 P、HiFiman HE400i などのオープン型ヘッドフォンの性能を表すために使われます。
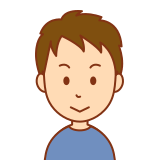
日本語でいう、音場に近い概念ですかね。
ナチュラル(Natural; 自然な)
これこそ、全てのオーディオ機器が達成しようとしている聖杯※ です。
原音に忠実にオーディオを再現することを意味し、たとえば、ヘッドフォンが出すギターの音が、ミュージシャンがあなたの目の前で演奏しているかのように聴こえる場合、それは「ナチュラル」と表現されます。この定義に間違いはありません。
※聖杯… 遠く手が届かず、達成が困難なことのたとえ
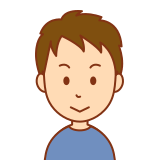
日本語でもよく使われる表現ですね。原音再生とか、原音忠実も。低価格帯の製品でよくみられるような味付けされたサウンドにも良いものはたくさんありますが、高級オーディオでは原音再生や臨場感にこだわる傾向があるようです。
アナリティカル(Analytical; 分析的な)
この用語は通常、音声出力の細部(detail; 全体に対しての細部)を定義するために使用されます。曲の多くの要素を明確に聞き取り、それらを区別することができるということは、良いヘッドフォンである証です。
しかしそれが過度になると、望ましくない効果を生みます。この「細部」への過度の強調は「分析的」であるとして知られています。理解するためにはやや複雑な用語ですが、良いシステムを使って良い音源から曲を聴き続ければ、いつかそれを理解することができます。
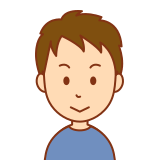
日本語の表現では「分解能」とか「解像度」などの言葉で評価されている部分ですかね。
バランス(Balance)
オーディオ出力が、高音や低音などの特定の周波数に偏らない場合は「バランスがとれた」出力となります。
適切に調整されたヘッドフォンは、Skrillexの曲を低音が全体を支配してしまわないように再生することができるので、バランスが良好な出力が実現できます。
アンバランスな出力は、周波数のうちどれが一つが支配的であり、曲の全体的なサウンドを乱してしまいます。
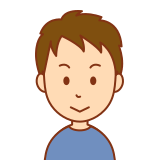
この定義では、均一(フラット)と同一の概念としてよいかどうかは言及されていませんね。
ブロウト(Bloat; 膨張/肥大化した)
ブロウトは望ましくないミッドバス(mid-bass)を批判する用語です。
これは、ミッドバスが過度で、ボロボロに聴こえてしまい調整が不十分であるように聴こえることを意味します。
簡単に言えば、低音が他の周波数と同様に肥大化して動いていない感じです。
例えば、ロックソングのバスドラムの音がビートが進んだことを知った後でさえも聴こえている場合、そのベースは「肥大化した」と表現されます。同義語は ‘マッディー’です。
ブライト(Bright; 明るい)
明るさ は通常、高音または高周波数に関連付けられている用語です。
それは高音をピークアウトさせ、それによってあなたのオーディオサウンドをより面白くて楽しいものにします。ほとんどの音楽愛好家は明るく聴こえるヘッドフォンを好みますが、度が過ぎると、あなたの音楽はひどく輝いているように聴こえてしまいます。
また、オーディオと同じように、明るさは相対的な用語であり、それを愛する人とそれを嫌う人との間で論争を引き起こす可能性があります。明確な勝者を決めることはできず、ただ個人的な好みです。
コンゲッション(Congestion; 混雑した)
空気が混雑するかのように、オーディオも混雑したように聴こえることがあります。
たとえば、あなたのオーディオがパイプを通り抜けながら互いに重なり合っている状態を思い浮かべて下さい。音声が ‘こもって(muffled )’ 聴こえると同時に、明快さが損なわれます。
そんなときはまず音源やケーブル接続をチェックしてください。音楽を自由に呼吸させてやる必要があります。
クリスプ(Crisp; パリッとした)
クリスプは、オーディオの精密性や正確性を表す時に使われる用語です。
小さな音が明瞭に表現され、高いレベルの正確さで生み出される様子です。
これは細部や明快さ、その他の要因が組み合わさって感じられる場合もあります。単純化すれば、ポテトチップスの砕ける音がはっきりと聴こえるようなイメージ。そんな風に音が明快に聴こえるならば、それはクリスプな音です。
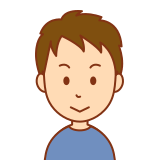
日本語でいう「歯切れのよい」とか「立ち上がりのよい」と似た概念かな?
ダーク(Dark)
高い周波数が弱く、目立たないように聴こえる場合、ダークな音と言えます。
それはブライト(明るい)な音の対義語として説明することができます。
高い周波数だけがあまり機能していない状況と考えて下さい。
ディケイ(Decay; 減衰)
ディケイは、オーディオノート※ が消える速度です。
たとえば、ギターの弦を弾いたとき、音が自然に消えるまでにかかる時間が減衰時間です。
優れたオーディオ出力は、曲のあらゆる減衰を適切に模倣(再現)します。減衰が不自然に聴こえる場合は、良いオーディオとはいえません。
※note… 4分音符、8分音符などが note と呼ばれます。よって流れで聴こえてくる「音 = sound」というよりは、「ド」「レ」など特定の一音や、その長さを指していると考えられます
デプス(Depth; 深さ、奥行き)
デプスは、楽器間の空間や距離感を指す言葉です。
奥行きが深くなるほど、あなたが感じる音の感覚は良くなります。
これはサウンドステージという用語に関連し、より具体的に定義することができます。
微妙な言葉ですが、重要な概念です。
ディテール(Detail; 細部)
細部のはっきりした音声は、音声の応答の鋭さ(sharpness)に寄与するでしょう。
あらゆる音(note)が聴こえ、オーケストラなどで様々な楽器が一緒に演奏されている場合でも、優れたディテールを備えたヘッドフォンを使用すると、個々の楽器に注意を払うことができます。
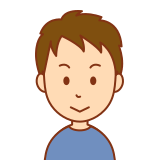
定位感、分離感と同義かと思われます。立体感にもつながりますね。
フォワード(Forward;)
音波再生が攻撃的にリスナーに向かってくるような表現で、リラックスしたオーディオの逆です。
これは望ましくない品質であり、主にオーディオを過度に積極的に駆動しているアンプが原因です。
ファン(Fun; 楽しい)
ファン・オーディオは、多くの音楽愛好家、特にインド音楽愛好家に好まれている一種のオーディオ再生です。
主に低音がヘビーな音楽を指します。あなたが単にオーディオを楽しみたいのなら、ファン・オーディオは魅力的です。低音と高音がエネルギッシュなため、ピュリスト(純粋主義者)はファン・サウンドのヘッドフォンを避けていますが、中音はくぼんでいます。
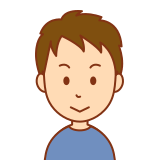
ドンシャリってことでしょうか?肯定的な意味のように思われますが、これはいまいちよくわかりません。
カラード(Coloured; 色付けされた)
カラードなサウンドは、特定の周波数がより高く、または低く再生されることで、自然な録音を再現したものは異なります。
すべてのヘッドフォンはある程度着色されていますが、ハイエンドのヘッドフォンはそれが薄く、アーティストが録音した通りに再生することを重視するため自然(ナチュラル)なサウンドになります。
ハーシュ(Harsh; きつい、トゲトゲした)
ざらざら、荒々しいオーディオを説明するために使用される用語。
高音にピークが追加されて、非常に不快になっている様子です。
耳はオーディオにおける悟りの境地の入り口となるものですから、丁寧に扱わなければいけません。
大音量で音楽を聴くことは、これとはまた異なる「きつさ」がありますが、今すぐ止めましょう。
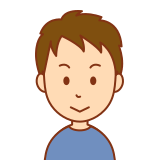
音量が低くても、大音量のときに感じるような不快感があるイヤホンはありますね…
イメージング(Imaging; )
イメージングとは、室内でのボーカルや楽器の配置です。
部屋にあるモノの配置が良くなればなるほど、部屋の外観は良くなります。
同様に、ボーカルと楽器が正しい位置に配置されていると感じられるときは、イメージングは優れています。イメージングについて話すとき、精神的なイメージを考えてください。それは大いに役立つでしょう。
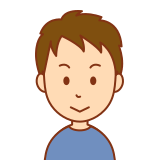
深さ、細部(解像度)などと近い印象ですが、いまいちはっきりしない概念ですね。ステレオ感?
ラッシュ(Lush; 豪華な)
ラッシュ は、豊かで繊細な音を指します。温かさと満腹感のあるオーディオとも。
もっと聴いていたいと思うような感覚になる音で、前述の通り良質な高音を含むオーディオ出力を表現する際にも使われます。
マイクロフォニックス(Microphonics; )
あなたのヘッドフォンケーブルが何かに擦れた時に、奇妙で邪魔な音を聞いたことがありませんか?その音はマイクロフォニックスと呼ばれています。
これはあたなのオーディオ体験を悪化させ、楽しいオーディオ出力を得られません。マイクロフォニックスが目立つヘッドフォンはお断りです。
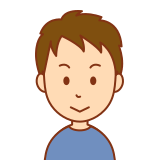
日本語でタッチノイズと呼ばれている現象のことですね。ケーブルを耳掛けすることで何とかなる場合も結構あります。耳掛け前提のイヤホンも多いですね。

ちなみにマイクロフォニックスは厳密には「電気部品を通る機械的振動の透過率」などが本来の定義らしいですが、もっと一般的に、服などにケーブルが擦れたときの不快な音のことに使われることも多いようです。
マッディ(Muddy; )
マッディーとは、歪んで不明瞭な周波数を表現するために使用される用語です。
高い周波数が弱く聴こえ、ディテールやクリスプの対義語です。
オープニス(Openess; )
パンチ(Punch; )
シビラント(Sibilant; )
サウンド・シグネチャ(Sound Signature; )
ティンバー(Timbre; )
トランスペアレント(Transparent; )
ウォームス(Warmth)






